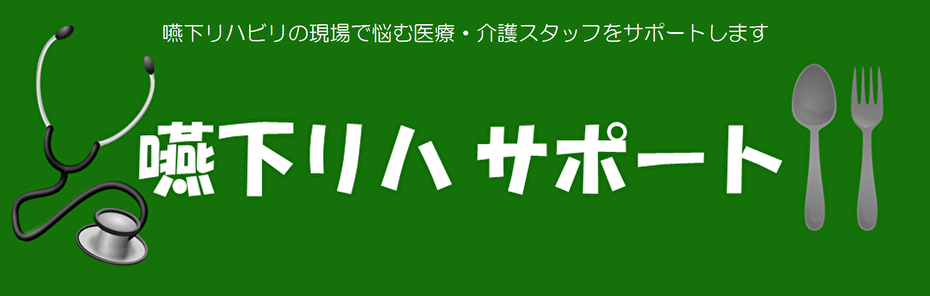3か月(全6回)でマスター!
嚥下リハビリ実力養成講座

第5回
楽食楽座を目指す!
誤嚥に負けない体を作る嚥下リハビリ
2025年度後期 募集中!
| タイトル | ➄ 楽食楽座を目指す! 誤嚥に負けない体を作る嚥下リハビリ |
| 開催日 |
2026年1月10日(土) |
| 時間・視聴方法 |
19時半~21時(Zoomによるオンライン視聴) ※当日のライブ配信に加え、今回初の見逃し配信を実施します ※見逃し配信はライブ配信の翌日か翌々日~2週間となります |
| 対象職種 | ST・看護師・栄養士・歯科衛生士・歯科医・OT・PTなど |
| 講師 | 大野木宏彰(ST) |
| 主催 | 嚥下リハサポート |
| 募集人数 | 30名程度 |
| 受講料 |
単回申し込み価格 4,000円(税込) セット申し込み特別価格 全6回 計20,000円(税込) ※PayPalによるオンライン決済 or 銀行振込 |
講師からのメッセージ
嚥下リハビリは、食べ物を用いる「直接訓練」と食べ物を用いない「間接訓練」に大きく分けられます。「直接訓練」については、嚥下評価や食事形態・姿勢・介助方法の工夫について、多くの書籍や研修会で学ぶことができます。しかし、「間接訓練」についてはどうでしょうか?アイスマッサージ、口腔ケア、嚥下体操などの画一的な内容を、「直接訓練」の“補助的”に学ぶ程度なのが現状ではないでしょうか。
「むせるからトロミをつけましょう」的に、パタカラ体操をしていたって効果がでることはないでしょう。「パンダの宝もの」や「寿限無寿限無」に替えてみたって同じです。当然ながら、病態に合わせた間接訓練が必要です。たとえば、咽頭クリアランスが悪いのであれば、姿勢の問題なのか、舌の筋力の問題なのか、咀嚼・食塊形成機能の影響なのか、など考えて訓練方法を選択していくわけです。反射遅延だけが問題であるなら、トロミなしで嚥下するために有効な方法・訓練、トロミをつけても誤嚥しやすい方に有効な方法などを検討・訓練していきます。そのために頸部聴診法を活用して「3つの嚥下機能」を把握しておく必要があるわけですね。
また、私は、現在の超高齢社会においては、「誤嚥リスクの軽減」より、「誤嚥性肺炎リスクの軽減」を意識した嚥下リハビリが重要になってきていると感じています。そのためには、身体機能にも目を向けた幅広い「間接訓練」が必要不可欠です。「舌が前に出ないからガーゼで舌を引きだす」、「飲み込みが弱いからシャキア訓練で頸部前面の筋を鍛える」など、目の前の口腔の問題だけをみて訓練を行っているのではうまくいかないことを、皆さん自身が感じていることでしょう。
このセミナーでは、頸部聴診による異常音から病態を読み解き、現場ですぐに使える訓練方法をお伝えしていきます。嚥下運動を支える頸部・肩甲帯の筋・関節の知識、姿勢や喀出能力を改善させるためのストレッチなど、“嚥下の土台からのアプローチ”について、触診や体験実習を豊富に取り入れながら学んでいきます。言語聴覚士や看護師をはじめ、「間接訓練を何とかしたい!」「嚥下リハに身体的なアプローチを取り入れたい!」という方はぜひご参加ください!
プログラム
1.「誤嚥リスク」と「誤嚥性肺炎リスク」を理解しよう!
2.フレイル・サルコペニアと摂食嚥下障害
3、肩甲帯からのアプローチ
4、 “根拠と効果のある”口腔リハビリ
5、症例・まとめ
●VE結果と発熱・CRP判定の関係
●口腔へのアプローチだけで終わっていないか?
●廃用症候群の嚥下への影響
●嚥下運動につなげる舌介助方法のコツ
●ストローを使った間接訓練・直接的間接訓練
●側臥位での後頭下筋群ストレッチ
● ・
● ・
などなど、触診や体験実習を豊富に取り入れながら学んでいきます。
備考
※セミナー時間は質疑応答も含め1時間半を予定しております
※セミナーQ&Aをご確認の上、お申し込みください